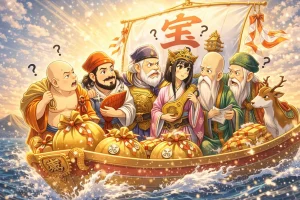稲荷信仰とは?伏見稲荷から商売繁盛まで|歴史に刻まれたエピソード集
稲荷信仰(いなりしんこう)は、日本において最も広く信仰されてきた民間信仰の一つです。稲荷神社は全国に3万社以上存在し、その総本宮が京都の伏見稲荷大社です。
稲荷神は五穀豊穣、商売繁盛、家内安全、交通安全、学業成就など多様なご利益を持つとされ、庶民から武士、商人に至るまで広く信仰されてきました。
今回はそんな稲荷信仰に関するエピソードをご紹介します。
稲荷信仰とは――日本人に最も身近な神
稲荷神は本来「宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)」という穀物の神とされており、『日本書紀』や『山城国風土記』にその名が見られます。

中世以降になると仏教の荼枳尼天(だきにてん)と習合しました。そのため、白狐にまたがる姿や狐を神使とするイメージが定着しました。
狐との関係
稲荷神の神使として有名なのが「白狐(びゃっこ)」です。

狐そのものが神であると誤解されることもありますが、狐はあくまで神の使い(神使)であり、神そのものではありません。狐が鍵や玉、巻物、稲穂などをくわえている姿は、神のご利益を象徴しています。
歴史的エピソード:太田道灌と稲荷信仰
1. 平将門と神田明神の稲荷
平安時代中期の武将**平将門(たいらの まさかど)**は、関東で独自の政権を打ち立てようとした人物で、朝廷からは反逆者とされました。将門は各地の神仏に祈願し、特に関東の稲荷神を厚く信仰したと言われています。
将門の乱の鎮圧後、彼の首塚近くに創建された神田明神には、将門の霊とともに稲荷神が祀られ、現在でも東京のビジネス街の守護神として多くの信仰を集めています。
2. 商人たちの「のぼり稲荷」――大阪・今宮戎との関係
江戸時代、大阪の商人たちは稲荷信仰を厚く持っていました。とくに伏見稲荷大社を詣でることは一大イベントでした。なかでも旧正月のころに行われる「初午(はつうま)」の日には、各地から稲荷詣でに人々が集まりました。

大阪では**今宮戎神社(いまみやえびす)**とともに稲荷信仰が習合し、「えびす・稲荷」の信仰が商人たちの間に広がりました。「のぼり稲荷」と呼ばれる商人が立てた幟(のぼり)は、自身の商売の繁栄と感謝を示すもので、今も神社の境内に残っています。
3. 江戸幕府の「御用稲荷」――愛宕神社と火伏せ信仰
江戸の**愛宕神社(あたごじんじゃ)**には、火伏せの神として信仰される火産霊神(ほむすびのかみ)とともに、稲荷神も合祀されています。
実は、江戸は火事の多い都市でした。そのため、火難除けと同時に商売繁盛を祈る人々がこの神社を訪れました。
特に「出世の石段」として有名な愛宕山の急階段を馬で一気に駆け上がったという**曲垣平九郎(まがき へいくろう)**の話は、江戸庶民の間で語り継がれ、稲荷信仰と武士の忠義・勇敢さが重ねて信仰されるようになりました。
商人と稲荷信仰:伏見稲荷の繁栄

江戸時代になると、特に商人階級の間で稲荷信仰が盛んになりました。伏見稲荷大社は商売繁盛の神として絶大な人気を誇り、全国から寄進された赤い鳥居が今も山全体に連なっています。これは商人たちが商売の成功への感謝と、さらなる繁栄を願って奉納したものです。
実在のエピソード:豊川稲荷と大岡越前
稲荷神社の中には仏教寺院と融合した形もあります。たとえば、愛知県の豊川稲荷は、正式名称を「妙厳寺」といい、曹洞宗の寺院です。ここでは荼枳尼天を稲荷大明神として祀っており、武士や庶民の信仰を集めました。
江戸時代の名奉行大岡越前守忠相(おおおか えちぜんのかみ ただすけ)。彼も豊川稲荷の信者であったとされています。実際に「稲荷信仰に助けられて名裁きをした」という伝説もあります。※この逸話の詳細は講談などで脚色されている場合もありますが、豊川稲荷の信仰者であったことは記録にあります。
参考文献・情報源
- 『山城国風土記』逸文(伏見稲荷の起源)
- 伏見稲荷大社 公式サイト:https://inari.jp
- 鳥居本幸代『狐と日本人―稲荷信仰の民俗学』(講談社学術文庫)
- 日本国史学会編『稲荷信仰と日本文化』(明治書院)
- 『江戸名所図会』豊川稲荷や江戸稲荷神社の記述あり
まとめ

稲荷信仰は、日本各地に根付いたもっとも庶民的で、かつ歴史的にも深い神道信仰のひとつです。農業、商売、武運、家内安全など、時代ごとに多様なニーズに応える形で受け入れられてきました。
実在の武将や商人、庶民の営みの中に根付いた稲荷信仰の姿は、私たちにとって「日常と神の距離の近さ」を再確認させてくれます。