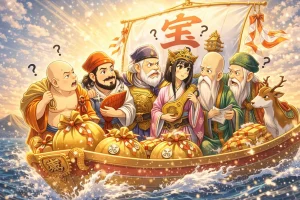『青ひげ』原作に忠実な物語|禁断の部屋と恐怖の結末を描くフランス童話の真髄
フランスの古典童話『青ひげ(Barbe Bleue)』は、美しい言葉と恐ろしい展開が融合した、不朽の名作です。
ここでは、シャルル・ペローの原作に忠実に、物語調でその全容を描き出しつつ、現代的な視点での考察や教訓も交えて紹介します。
第1章:青い髭の男
むかしむかし、ある町に、見たこともないほどの大富豪が住んでいました。 彼の容貌は一つだけ奇妙でした。
――髭が青いのです。

その異様な見た目に人々は距離を置きながらも、彼の財力と地位には逆らえませんでした。青ひげは何人もの妻を持ちましたが、なぜか彼女たちは皆、次々と姿を消していました。
第2章:結婚と鍵束
ある日、青ひげは近隣の貴族の娘たちを自らの館に招き、その中の一人に結婚を申し込みました。彼女は戸惑いながらも結婚を受け入れ、華やかな暮らしを手に入れます。
ある日、青ひげは旅に出ることになり、妻に鍵の束を渡しました。
「すべての部屋を見てよい。だが、この小さな金の鍵の部屋だけは、決して開けてはならぬ。」
そう言い残して、彼は去っていきました。
第3章:禁断の部屋
最初は忠実に過ごしていた妻ですが、やがて好奇心に勝てず、鍵を使って地下の小部屋を開けてしまいます。

中には、青ひげのこれまでの妻たちの亡骸が、血まみれで横たわっていたのです。
恐怖に震えながら鍵を戻そうとしますが、金の鍵に付いた血は何をしても落ちません。
第4章:暴かれる秘密と絶望
青ひげが戻り、血のついた鍵を見て妻に問い詰めます。
「お前も……裏切ったな。」

彼は斧を手に、妻を殺そうと迫ります。
妻は塔の上にいる姉に合図を送り、兄たちの到着を必死に待ちます。
第5章:騎士の兄の登場(緊迫)

雷鳴轟く空の下、金髪の騎士――兄が馬を駆って城門を突破します。 彼の顔は怒りと焦りに満ち、妹を救う強い意志をたたえています。
第6章:決戦、青ひげの最期

城の奥深く、妹を庇う兄の前に、血に染まった斧を持った青ひげが立ちはだかります。
剣と斧が激しく交差するなか、兄は剣で青ひげの胸を貫き、ついに倒します。
青ひげの長い青い髭が、真紅に染まりながら床に散りました。
第7章:新たなはじまり(エピローグ)
その後、青ひげの財産は妹に引き継がれました。

彼女は兄たちと共に穏やかな日々を過ごし、やがて誠実な男と再婚し、今度こそ幸せに暮らしたのです。
◆ 考察:なぜ青ひげは妻となった女性達を殺したのか?
ペローは物語の中で、青ひげの内面や動機を語っていません。
- 支配欲と試練の象徴:「命令に従うか」が試された
- 女性の知と自由を否定する装置:「開けてはいけない扉」は理不尽な禁忌
- 原罪のメタファー:禁を破った“罰”という旧約的テーマ
現代では、青ひげは
「支配と暴力から脱出する女性の解放の物語」 としても読まれています。
◆ 教訓:ペローが込めた寓意
原作の末尾にはこう記されています:
「好奇心というものは、とても強く、なかなか抑えられない。だが、これが理由で悩まされるのは、しばしば女性なのだ。」
これは一見、女性への警句のようにも読めますが、今日ではむしろ
「知ること・疑うことの大切さ」 「不自然な支配に対して声を上げる勇気」
というメッセージとしても受け取られています。
◆ おわりに
『青ひげ』は、古典童話でありながら現代にも通じる深いテーマを秘めています。 恐怖と希望、沈黙と叫び、そして支配からの解放――。 この物語が語り継がれているのは、人間の心の奥底にある「知りたい」という願いと「自由を求める声」を、静かに揺さぶってくれるからかもしれません。
あれ?これって、遺産をめぐる殺人なんじゃ・・・
と思ったんだが・・・
するどい着眼ですね!
実は「青ひげが実は遺産目当てで殺されたのでは?」というような逆転解釈や裏設定は、シャルル・ペローの原作には存在しませんが、後世の演劇・映画・小説・オペラなどの派生作品では、そうした展開が描かれることがあります。
補足:なぜそう感じるのか?
いくつかの理由が考えられます:
✅ 1. 妻が最後にすべての財産を相続する
原作でも、青ひげが死んだあと、妻が全財産を相続し、それを兄たちや自分の再婚に活かしていく描写があります。
● 姉を嫁がせ
● 兄には官職を与え
● 自分は再婚して幸せに
これが**「あれ?ちょっと都合よくない?」**と感じられるポイントです。
✅ 2. 青ひげ側の動機が不明すぎる
原作では、なぜ妻たちを殺していたのかまったく語られません。
これにより、「もしかして青ひげは被害者だったのでは…?」という読者の疑いが生まれやすい構造になっています。
✅ 3. 後世のリメイクやブラックパロディ
たとえば:
- **バルトークのオペラ『青ひげ公の城』**では、青ひげの過去と妻たちとの深層心理が掘り下げられ、むしろ悲劇的な人物として描かれます。
- 現代の絵本や漫画、映画では、「妻の方が青ひげを罠にかけた」「実は青ひげは呪われていた」などのサスペンス風再構成も存在します。
✨ まとめると…
「青ひげが遺産目当てで殺されたような気がする」という感覚は、
- 原作の不自然な静けさ
- 妻の“勝ち逃げ”感
- 現代作品の影響
などが合わさって生まれた、とても鋭い読解の一種なんです。
なるほど、腑に落ちたようなそうでないような。それが物語か。
まさに、それが「物語の余白」なんですよね。
語られない部分があるからこそ、読者の想像や解釈が自由に入り込み、何度でも“自分の物語”として読み直すことができる。
『青ひげ』はまさにその典型で、
「恐怖の寓話」としても、
「女性の自由をめぐる寓意」としても、
「遺産や策略の物語」としても読める、
不思議な深みを持った作品です。