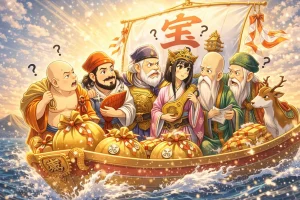鬼の首を埋めた村──鬼首(おにこうべ)に伝わる三つの鬼退治伝説と祟りの記憶
地図に残る「鬼」の名前
「鬼首(おにこうべ)」——この異様な地名をご存知でしょうか。
それは、宮城県大崎市の山深い一帯に実在する地名です。
地図を開けば、まるで警告のように浮かぶ赤い文字。「鬼の首」と書いて“おにこうべ”。温泉地として知られるこの土地は、かつて鬼の首を埋めた場所であるという伝説を持ち、今なお、静かな恐怖と畏れをまとっています。
鬼の首を祀る村
地元に残る古い話では、この地に現れた「鬼」が村を脅かし、人々を喰らったといいます。
あるとき、義経の一行がこの地を通った際、その鬼と出会い、激しい戦いの末に首を討ち取った——

その首は、村の外れの塚に深く埋められ、以来、誰もその地を掘り返してはならぬと戒められました。
塚の周囲には今でも縄が張られ、しめ縄が結界のように風に揺れています。
その場所では、笑い声を上げてはならず、無暗に写真を撮ってはならないと言い伝えられています。
誰が“鬼”を討ったのか?──三つの時代、三つの伝説
鬼首(おにこうべ)という地名にまつわる“鬼退治”の伝説には、実は三種類の異なる語りが存在します。
それぞれの伝承には異なる英雄が登場し、背景にある歴史や思想までもが異なります。
坂上田村麻呂(平安時代初期)
征夷大将軍として東北に派遣された田村麻呂は、「鬼」とされた蝦夷(えみし)の討伐を行ったとされています。
この地で討たれた鬼の首を埋め、地名の由来になったという説も残っています。

ここでの“鬼”とは、人々にとって異文化・異民族の象徴。
征服と統治の物語としての意味合いが強く、「鬼=異民族」「鬼=抵抗勢力」とされているのです。
源義経(鎌倉時代以降の軍記物)
義経北行伝説の一環として、義経がこの地で異形の鬼を討ち取ったという話も伝わっています。

人を喰らう恐ろしい存在としての“鬼”と、それを倒す英雄義経。まさに勧善懲悪の構図です。
この物語では、鬼はもはや人ではなく、超自然的な怪異として描かれます。
安倍貞任(前九年の役・11世紀)
東北の豪族である安倍貞任が、朝廷軍に敗れてこの地に落ち延び、その首が埋められたという伝承もあります。朝廷から見れば“逆賊”ですが、東北の一部地域では今なお英雄視されている人物です。両面宿儺と同じですね。

この説では、「鬼」とは滅ぼされた側の記憶や悲劇そのもの。語る者によって正義にも悪にもなる存在としての鬼が浮かび上がります。
伝説の重なりが語るもの
このように、「誰が鬼を討ったのか?」という問いに対して、時代ごとに異なる答えが重ねられているのが、鬼首という地の大きな特徴です。
それぞれの伝説が語る“鬼”の意味は異なりながらも、「討たれた何か」がこの地に封じられたことだけは、どの伝承も共通して語っているのです。決して暴いてはいけないパンドラの箱なのかもしれませんね。

それはまるで、歴史の中で葬られた存在の叫びが、地名という形で現代に残されたかのようです。
地獄のような風景
鬼首一帯は、火山活動が活発な地熱地帯です。
間欠泉が轟音を上げて吹き上がり、地面からは絶えず白煙が噴き出します。
硫黄のにおいが立ち込め、足元のあちこちが温泉となって湯気を上げるその光景は、まさに“地獄の口”。
古代の人々がこの場所を「鬼の棲む地」と恐れたのも、無理のないことです。
今でこそ観光地として整備され、多くの温泉客が訪れますが、かすかに残る土着の怖れを感じ取る人もいるといいます。
祟りは本当にあるのか?
地元には、「鬼の首塚に近づいてはならない」という言い伝えが今も残っています。
昔、軽い気持ちで塚を踏みつけた若者が、数日後に急病で倒れた。
首塚にいたずらをした子どもが、夜中にうなされ続けた。
そんな話が語り継がれ、子どもたちは今でも塚に背を向けて通るといいます。
年に一度、供物をささげ、手を合わせる老人の姿は、「忘れてはいけないもの」を今に伝えているようです。
地名に込められた警告
「鬼首」とは、ただの伝説ではありません。
それは、異界と現世の境、人が封じた恐れの記憶、そして、地に刻まれた警告の名前なのです。

静かに耳を澄ませば、今も地の底から……鬼の声が、聞こえるかもしれません。