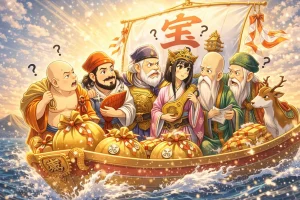両面宿儺~飛騨地方に伝わる英雄譚と歴史に刻まれた鬼神の姿をAIと語ってみたよ
両面宿儺って知ってる?
はい、両面宿儺(りょうめんすくな)は日本の古代伝説に登場する妖怪や悪神の一種として知られています。奈良時代の『日本書紀』や『飛騨国風土記』に記述があり、両面宿儺は二つの顔と四本の腕を持つ恐ろしい存在として描かれています。
特に飛騨地方(現在の岐阜県)に関連が深く、悪逆無道な行いをして人々を苦しめていたとされています。しかし、一部の伝承では両面宿儺が善良な存在であり、人々を救ったという説も存在しています。
最近では、両面宿儺は漫画やアニメ作品(『呪術廻戦』など)でも取り上げられており、フィクションの世界で新たな解釈がされていますが、元々は古代の神話や伝承に根ざした存在です。
今回はこの両面宿儺について、悪と善の伝承の2つを見ていきます。
最初は邪悪な化身として描かれる両面宿儺から、その後続けて善良な両面宿儺伝承をといてみるね。
悪鬼の両面宿儺伝説
むかし、飛騨の山々に恐ろしい化け物が住んでいました。その名は両面宿儺。
前にも後ろにも顔を持ち、四つの腕を振りかざすその姿は、人々に恐怖を与えました。その姿はまさに鬼神そのもの。
彼は村々を襲い、食料を奪い、村人たちを無理やり服従させました。
両面宿儺の噂は山を越え、遠くまで広がりました。『宿儺に逆らえば命はない』と恐れられ、村人たちは震えながら日々を過ごしていたのです。

彼の力は単なる腕力だけではありません。
両面宿儺は自然の力をも操り、近くを流れる大河の堤防を破壊したのです。
水は激しく村々を襲い、家々が流され、田畑は荒れ果てました。
村人たちは命からがら逃げ延びたが、両面宿儺に立ち向かう術はありません。
彼は高笑いをしながら、洪水で崩れた大地を支配したのでした。

※当時の人はこのくらいの誇張で伝わってて怖かったんだと思います。情報が少ないからこその恐怖ですね。
洪水は、古代の人々にとって非常に恐ろしい災害でした。特に、農業に依存していた社会では、川が氾濫して田畑が流されることは生命に直結する大問題でした。そのため、洪水のような自然災害は、超自然的な存在や神々、悪霊の仕業として説明されることが多かったのです。
中央の都にこの報告が届くと、天皇は討伐を命じました。選ばれたのは、腕に覚えのある剛の者たち。彼らは飛騨の山々を越え、両面宿儺の住む山に向かいました。

討伐隊は、両面宿儺と対峙したが、その強大な力に押され、一度は敗北を喫しました。

だが、討伐隊のリーダーは諦めませんでした。
神の加護を受けた剣を携え、再び戦いを挑んだのです。
激しい戦いの末、ついに両面宿儺は討たれ、その支配も終わりを告げました。

討伐隊は見事、両面宿儺を打ち倒し、平和をもたらしたのでした。

さて、これがおおざっぱですが、両面宿儺の良く知られたストーリー。
ここからは、一部の地域に伝わるお話しです。さっきまでのストーリーとは180度違うのでご注意くださいね。
善良な神として崇められた両面宿儺
むかし、飛騨の山々に住んでいたのは、特異な姿をした男でした。
その名は両面宿儺。
彼は、二つの顔と四つの腕を持っていたが、心優しく、人々を守る力強い存でした。
ある年、突然の大雨が村を襲い、大河は氾濫し、村々が水に沈もうとしていました。
村人たちは助けを求めたが、誰も彼らを救うことができなかったのです。

その時、両面宿儺は立ち上がりました。彼は一人で大きな石を運び、堤防を築き始めました。その四つの腕で次々と石を積み上げ、激しい川の流れを食い止めたのです。
村人たちはその姿を見て驚き、感謝の声を上げました。
『両面宿儺様が、我々を救ってくれたのだ!』と。
堤防が完成すると、洪水は収まり、村は無事に守られました。

両面宿儺はその後も村のために尽力しました。
病気が流行れば、自らの薬草の知識で治療し、作物が不作の年には村人に農業の技術を教えました。

村人たちは彼を敬い、飛騨の守護神として崇めるようになりました。両面宿儺の名は、村を救った英雄として語り継がれることとなったのです。

なぜここまで異なる伝承が残っているのか
なぜここまで内容が異なる話が伝承されているのか。様々な見解があるけど、有力とされているのは、当時の政治背景だよね。
両面宿儺が悪神として伝えられている背景には、当時の政治的な事情や中央政権の意図が影響している可能性が考えられます。特に、『日本書紀』に記載されている両面宿儺に関する記述は、彼を「反逆者」や「悪の存在」として描いていますが、これが飛騨地方の実際の人物や勢力を抑えるための計略だったのではないかという説もあります。
当時の飛騨地方(岐阜県)は山岳地帯で、中央政権の支配が及びにくい地域でした。そのため、独自の文化や宗教観が根付いていた可能性があります。
そうした地域の有力者や英雄的な人物が、中央から見れば「反乱者」や「異端者」とみなされ、悪いイメージを付けられることは歴史上よくあることです。
例えば、飛騨地方の伝承において両面宿儺が善神として崇められている一方で、中央の記録である『日本書紀』では彼が暴虐な存在として描かれています。
この矛盾は、中央政権(天皇を中心とした朝廷)が飛騨地方を統治下に置こうとする際、両面宿儺を「敵」として悪く描き、中央への服従を促すための計略であった可能性があります。
こうした中央政権による「敵対者」の悪化戦術は他の例にも見られます。
例えば、地方の英雄が中央の敵とされたり、支配が及ばない土地の神や伝説が後に悪神や妖怪とされたこともあります。
両面宿儺も、当時の天皇や朝廷が地方統治のために利用した政治的な宣伝の一環だった可能性があるわけです。
つまり、両面宿儺が悪神と伝わった理由は、当時の権力構造と地方統治の文脈を考慮すると、天皇や中央政権による計略の一部であった可能性があります。
ちなみに、あの有名な土蜘蛛は、古代の『日本書紀』や『古事記』に登場する異形の存在ですが、これは元々「土着民」を意味する言葉だったと言われています。
つまり、土蜘蛛は中央の支配に従わない地方の部族や豪族を指しており、彼らが後に「異形の化け物」として物語に登場することになったとされています。
物語では、強力な武士が土蜘蛛を退治することで中央の支配を強化するという形で語られています。

これらの例に共通しているのは、地方の有力者や豪族が中央の権威に反抗し、その結果として「妖怪」や「魔物」として語り継がれるようになったことです。
これは、中央政権が自らの正当性を主張し、地方を征服・統治するためのプロパガンダの一環だったと考えられます。
つまり、実際には勇敢であったり、地域で支持されていた人物が、政治的な理由で「化け物」として伝えられたということが多いわけです。
洪水を防ぎ、農業を安定させることは神の偉業
善悪の2つの話に共通してあるのは、「洪水」の存在です。
悪鬼の方は洪水を起こしましたが、善良な方は洪水を止めた。これは全く正反対のことですよね。
洪水や自然災害はまさに「化け物の仕業」や「神々の怒り」として捉えられることが多かったのです。八岐大蛇も水害だったという説がありますよね。
洪水は、古代の人々にとって非常に恐ろしい災害でした。特に、農業に依存していた社会では、川が氾濫して田畑が流されることは生命に直結する大問題でした。
だからこそ、両面宿儺が英雄として洪水から村を守ったという話は、自然の力に対抗できる存在として彼を神格化し、守護者として祀る理由の一つだったかもしれませんね。
逆に、悪鬼として伝えたい場合は、洪水を起こして人々を苦しめたとすれば良いということになります。
事実は知りようもありませんが、洪水という大災害が人々を苦しめており、救いの手を求めていたのは間違いありません。
先人たちの知恵が今の日本を作り上げたのですが、その裏には、権力による知らざれる悲劇が起きていたのかもしれませんね。